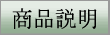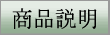|
【商品説明】
たなびく雲か霞の向こうに杉林をたたえた山々が見え、手前には川が流れ、さらに手前側には平地があるといった里山の風景が表された九寸名古屋帯です。
少し紅葉したような木の葉が一番近くに描かれていて、それによって全体に遠近感が生まれ、風景に広がりをもたらしているように見えます。
木版染はほうのきや桜の木で作られた3、4cm角の大きさの版木に染料をつけて、ひとつずつの小さな柄を置いていき、その連続で模様を作り出していくものです。
ひと柄ずつ鎚でたたいて染め出していくそうですが、その力加減によってニュアンスが変わるため、それを上手く使い分けられてこそ素晴らしい作品が生まれるそうです。
スケッチを重ね、構想を練ってデザインを考え、実物大の下絵を描いて、それに沿って版木を操り、染め出していく、非常に時間と根気と技術を要するものであることは確かです。
こちらの作品でも、たなびく雲の輪郭は1.5cmの長さの線の集合で描かれていて、杉林の部分も染め重ねられて臨場感を出されているようです。
小山さんの作品は幼い頃に過ごした長野の山と川のある風景が多く見受けられ、自然の風や光、水の流れの変化などを作品に込められたかったようです。
眺めても、身に着けても美しいという事をテーマにされていたようで、こちらの作品も活き活きとして新鮮で、すぐにでもお気に入りの紬のお着物に合わせてみたいと思ってしまいます。
地染めの藍味のあるグリーン・高麗納戸色は、お着物との相性が良くとても魅力的です。
お稽古事にも、ご友人とのお食事の会や音楽鑑賞、美術鑑賞にも、また街着としてもお召いただけます。
帯という小作品の中に込められた昭和の巨匠の技と、洗練されたデザインや色使いに改めて感動する、希少性も高いおすすめの作品です。
【小山保家】
1903年 長野県上田市に生まれる
1920年 両親と上京
1924年 川端画学校日本画科卒業
1925年 石塚市太郎先生に友禅の教えを受ける
1945年 萌黄会(のち萌木会)会員として10年間芹沢銈介先生に型絵染を学ぶ
1948年 国展に初入選
1953年 版染めの研究を始める
1959年 日本伝統工芸展に木版染の訪問着を出品
その後も続けて出品・受賞を重ねる
1973年 社団法人日本工芸会理事に就任
その後も伝統工芸展出品・美術館や文化庁の買い上げとなる。
地の色は高麗納戸「#2c4f54 color-sample.com」、
雲の色は暁鼠(あかつきねず)「#d3cfd9 color-sample.com」、
山の色は白橡(しろつるばみ)「#cbb994 color-sample.com」、
薄鼠「#9790a4 color-sample.com」、
木の色は天鵞絨(びろうど)「#2f5d50 color-sample.com」、
松葉色「#6b804b color-sample.com」、
木の葉の色は褐色(かっしょく)「#8a3b00 color-sample.com」
をご参照下さい。
|