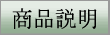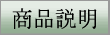|
【商品説明】
こちらは重要無形文化財「木版摺更紗」保持者、鈴田滋人さんの九寸名古屋帯の作品です。
日本には、古くから珍重され、現代では古渡と呼ばれる非常に貴重な「裂」があり、そのひとつに更紗があります。
更紗は16世紀末から18世紀にかけて日本に輸入された、インド、ジャワをはじめ、ペルシア、さらにイギリス、オランダなどのヨーロッパ製を含む外国の木綿の模様染めの総称で、その技法は主として手描き、木版、銅板、蝋防染によるものでした。
非常に高価であった事もあり、それをお手本にして、さらに日本人好みの色柄のものが各地で作られるようになりました。
それらは長崎の鍋島更紗・天草更紗、大阪の堺更紗、京の堀川更紗など、和更紗と呼ばれて親しまれました。
鈴田さんは、鍋島更紗の研究と復元に長年取り組まれた、故・鈴田昭次さんの後を継ぎ、木版と型紙を使用する「木版摺更紗」の研究を続けられ、2008年に人間国宝に認定されました。
木版と型紙を併用する鍋島更紗は世界でも類を見ない技法で、江戸時代には鍋島藩の保護のもと諸大名や幕府への献上品として盛んにつくられました。
その技法は木版摺りと型紙摺りを併用した独特のもので、色染めも精巧を極めたそうです。
しかしながら数百年の時間が経過し、紛失した資料や伝聞でしか残っていないものなどもあり、鈴田氏はお父様の照次氏の時代から二代に渡って試行錯誤を繰り返し、その復元に至るまでには大変なご苦労があったようです。
約10cm角の木版を全身の力を込めて連続して押していき、染めていくといった作業は、想像もできないくらい気力を要する事と思いますが、それをぶれることなく精緻な模様に染められるという技は決して他の方には真似のできない事なのでしょう。
そんな力強い作業を経て染められた作品には、そういったご苦労とは裏腹に優しさと気品があり、見る人を魅了します。
そして実際に身につけられた時にはハッとするほど輝くような華やかさで、着る人を素敵な装いに導きます。
他には存在しない個性と品格を持った、素晴らしいおすすめの逸品です。
【鈴田滋人】
1954年 佐賀県鹿島市生まれ
1979年 武蔵野美術大学日本画学科卒業
1981年より「鍋島更紗」の研究と復興に力を注いだ父・鈴田照次氏の後を受け木版摺更紗の研究を続けられ、その技法を高度に体得、独自の作風を確立されました
1982年 日本伝統工芸展初入選(以後連続入選)
1985年 日本工芸会正会員となる
1994年 東京国立近代美術館工芸館にて「現代の型染」に出品
1996年 日本伝統工芸展 日本工芸会奨励賞受賞、同作品文化庁買上げ
1998年 日本伝統工芸展 NHK会長賞受賞、同作品文化庁買上げ
2003年 伝統文化ポーラ賞 優秀賞受賞
2007年 大英博物館にて日本伝統工芸展50周年記念展「わざの美」に出品
2008年 最年少で「木版摺更紗」の重要無形文化財保持者に認定されました
地の色は青丹(あおに)「#99ab4e color-sample.com」、
模様の色は鉄色「#005243 color-sample.com」、
鶸色(ひわいろ)「#d7cf3a color-sample.com」、
赤丹(あかに)「#ce5242 color-sample.com」
をご参照下さい。
|